お赤飯のレシピをご紹介します。
炊飯器を使った赤飯の簡単な炊き方です。
炊飯器をつかう最大のメリットは、やはり手軽さです。
炊飯器をつかうと、豆の茹で汁にもち米を浸しておく必要がありません。
茹で汁と一緒に炊くだけで色良く仕上がるので、思い立ったときにすぐに作れます。
お赤飯といえば蒸し器を使うのが昔ながらの定番で、炊飯器で炊くと柔らかくなりがちですが、水加減などに注意すると、炊飯器でもおこわらしく美味しく仕上がります。
もち米の量を選択
このレシピは、使用するもち米の量を選べるようになっています。
分量が変わっても、作り方はまったく同じです。
材料
| もち米 | 2合 |
| ささげ(又は小豆) | 40g |
| 塩 | 小さじ2/3 |
| 水 | 500ml |
| 黒ごま・塩 | 好みで適量 |
レシピ・作り方

- きれいに洗う

- ザルに上げる
- ① ささげ(又は小豆)をきれいに洗い、ザルに上げて水気を切ります。
補足:ささげと小豆の違い

- 豆を鍋に入れる

- 火にかける
- ② ささげを鍋に入れて水を加え、火にかけます。
水の量は、もち米2合を炊く場合は500ml、3合を炊く場合は600mlです。

- 茹でる

- 硬さの目安
- ③ 沸騰したら弱めの中火にして、15〜20分ほどかけて、指でつぶせるくらいの少し硬めに茹でます。

- ボールに移す

- 冷ます
- ④ 茹で上がったささげを茹で汁ごとボールに移し、茹で汁をお玉で何回かすくって落として空気に触れさせたうえで、20〜30分ほど置いて冷まします。

- ザルに上げる

- 汁と豆を分ける
- ⑤ 冷ましたささげをザルに上げ、茹で汁と豆を分けます。

- 米を研ぐ

- 水気を切る
- ⑥ もち米を研ぎ、ザルに上げて水気を切ります。
補足:米を浸水させない

- 茹で汁を加える

- 水を注ぐ
- ⑦ もち米を炊飯器の内釜に入れて、ささげの茹で汁を加え、「おこわの目盛り」まで水を注ぎます。
もち米2合を炊く場合は、2合の「おこわの目盛り」まで水を注ぎます。
3合の場合は、3合の「おこわの目盛り」まで注ぎます。
補足:おこわの目盛りがない場合

- 塩を加える

- 豆を広げる
- ⑧ 塩を加え、ささげを広げて、「おこわモード」で炊きます。
「おこわモード」がない場合は、普通の「白米モード」で炊きます。

- 炊きあがり

- さっくり混ぜる
- ⑨ 炊き上がったお赤飯を、しゃもじでさっくりと混ぜたら完成です。

お好みで、黒ごまや塩を軽く振っていただきます。
豆の味がしっかりと感じられる、風味豊かなお赤飯。
油断するとついつい食べすぎてしまう美味しさです。
蒸し器とくらべると調理時間は炊飯器のほうが断然短いので、忙しいときには、今回のように炊飯器で作るのがおすすめです。
レシピの補足説明
地方によるお赤飯の違い
お赤飯にささげと小豆のどちらを使うかは地方によりますが、私(やまでら)が暮らしている関東地方では、ささげを使うことが多いです。
小豆は腹割れ(煮崩れ)しやすいので使いにくく、また、「腹割れ」が縁起が悪いと言われているためです。
ささげと小豆の違い
お赤飯はささげでも小豆でも作れますが、ささげを使って作るのがおすすめです。
ささげの方が、豆の形がキレイに残りやすいうえに、赤色も濃く出やすく、また風味もしっかりしているように感じます。
ささげと小豆は国産がおすすめ
ささげや小豆は、ぜひ国産のものを選んでください。
廉価な輸入品もありますが、私の経験では、輸入品は赤い色が付きにくいうえに煮崩れしやすいです。
なお、国産と輸入品は、乾燥状態の見た目でもある程度判断できます。
下の画像は国産と輸入品のささげを比較したものですが、色が淡いものは、輸入品である場合が多いです。

豆のアク抜きは不要
豆を茹でる前に一度茹でこぼしてアク抜きするレシピもあります。
ただ、私は、マクロビオティックを学んだことがきっかけで、茹でこぼすのを止めてしまいました。
茹でこぼさない方が、むしろ味が濃く感じられて美味しいと思っています。
豆を少し硬めに茹でる
ささげ(又は小豆)は、茹でた後にお米と一緒に炊くので、中まで火を通しつつも、少し硬めに茹で上げます。
茹で汁を空気に触れさせる理由
ささげ(又は小豆)の茹で汁に空気を含ませると、発色が鮮やかになります。
もち米を浸水させない
研いだ後に、もち米を浸水させる必要はありません。
もち米は吸水性が高く、浸水させずに炊く方が、おこわらしさが出ます。
おこわの目盛りがない場合
炊飯器でお赤飯を炊く際には、通常の水加減よりも控えめにします。
水加減の目安は、「おこわの目盛り」までです。
おこわ用の目盛りがない場合は、ささげの茹で汁と水を合わせたものを、もち米2合なら300ml、3合なら450ml加えると、おこわらしい食感に仕上がります。
すこし柔らかめの食感がお好みの場合は、2合なら300〜360ml、3合なら450〜540mlの間で調整してみてください。
お赤飯を食べる日
お赤飯は、おめでたい時はもちろんのこと、お彼岸にもよく食べられてきました。
「入りぼた餅、明け団子、中の中日小豆飯(お赤飯のこと)」といって、お彼岸のちょうど真ん中の日に食べられてきました。







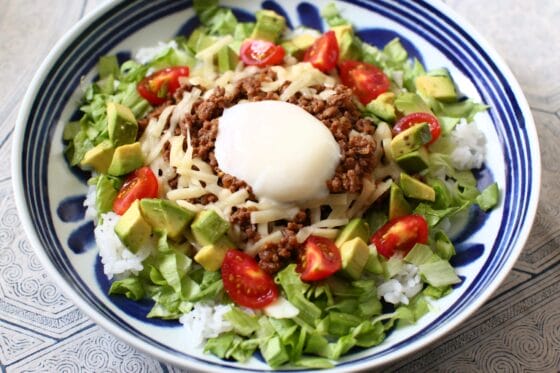



このお料理についてのご感想などをお寄せください。
サイト運営の参考にさせていただきます。
頂いたコメントには、2〜3日以内にメールアドレス宛に回答いたします。(詳細)
メールアドレスの入力ミスにご注意ください。
なお、頂いたコメント及びその後のメール等でのやり取りは、この欄でご紹介させていただく場合がございます。